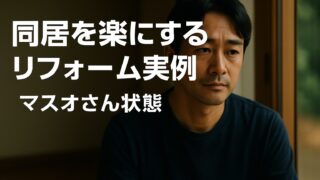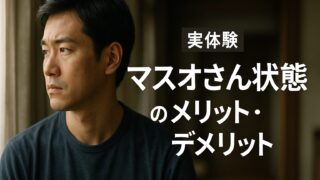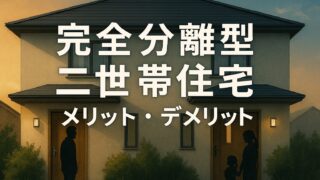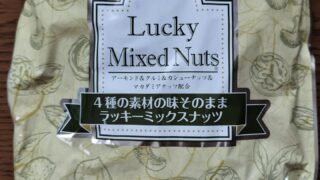【実体験】二世帯同居の生活費は月いくら減る?分担ルールと光熱費・食費のリアル公開
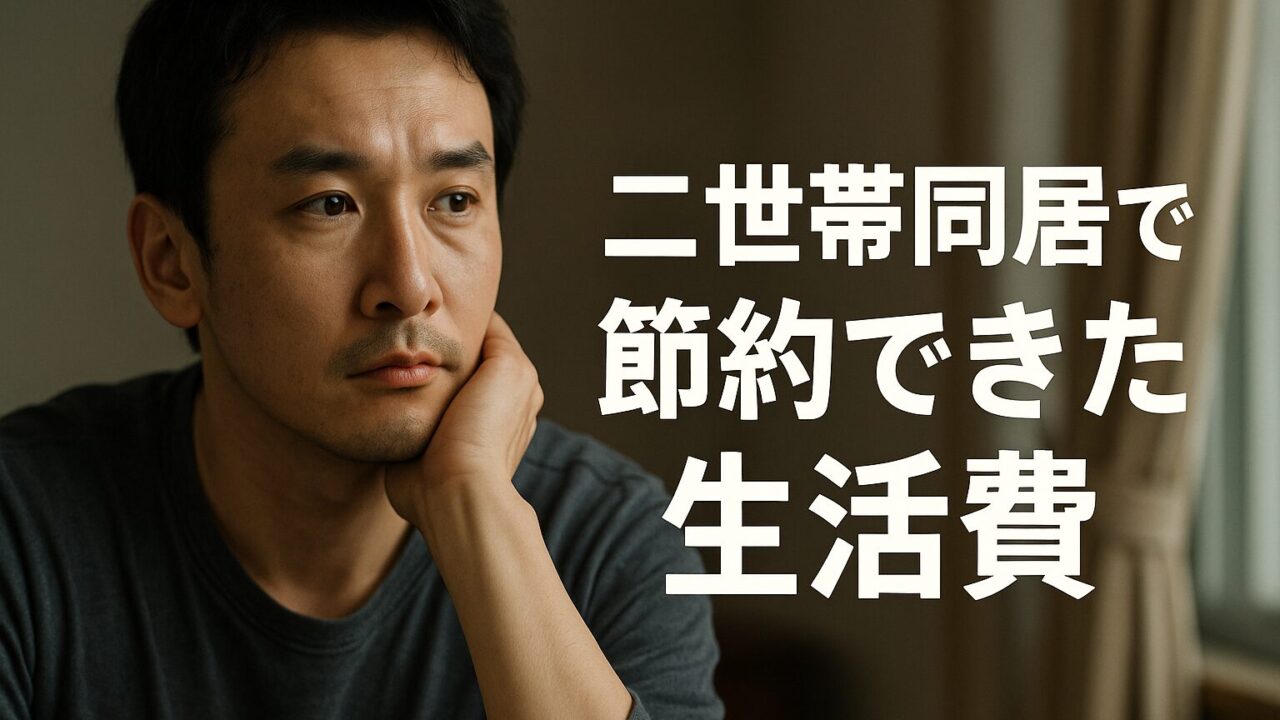
この記事では、僕がいわゆる「マスオさん状態」で二世帯同居を始めてから、生活費がどう変わったのかを実数ベースでまとめます。
先に結論から言うと、我が家は同居によって月あたり約6万円、年間だと70万円以上の家計差が出ました。
ただし、二世帯同居は「節約できて終わり」ではありません。お金のルールが曖昧だと、節約以上にストレスが増えるのも事実です。
この記事では、水道代・電気代・ガス代・食費・日用品・通信費まで、同居で変わったポイントと、揉めないための分担ルールを“テンプレ化”して解説します。
結論|二世帯同居で一番効いたのは「住居費」。でも鍵はルール設計
二世帯同居で家計が大きく変わる理由はシンプルで、家賃(または住宅ローン)が実質ゼロになりやすいからです。
一方で、光熱費や食費は「人数が増えたから単純に割ればOK」とはならず、生活スタイルの差でモヤっとしがち。
だからこそ、節約を“再現”するには、最初に分担ルールを決めて見える化するのが最短ルートでした。
我が家の前提|家族構成・家のタイプ・同居スタイル
我が家は、妻の実家に僕・妻・子ども2人の4人家族が同居している「マスオさん状態」です。
義両親と一緒に5LDKの戸建て住宅で暮らしており、完全分離ではなく部分共有型の二世帯同居(キッチン等を共有するスタイル)です。
この前提が近いほど、この記事の数字や考え方は参考になると思います。
揉めない鍵はここ|生活費分担ルールの決め方(手順)

僕が強くおすすめしたいのは、同居スタート直後(できれば同居前)に、「誰が・何を・どの基準で払うか」を言語化しておくことです。
手順1:費用を「固定費・変動費・将来費」に分ける
- 固定費:通信(回線/固定電話)、保険、固定資産税など
- 変動費:電気・ガス・水道、食費、日用品など
- 将来費:外壁・屋根・給湯器、家電買い替え、メンテ費(排水管・シロアリ等)
この3分類にすると、「毎月の精算」と「数年後の大きい出費」を混ぜずに話せるので、一気に揉めにくくなります。
手順2:分担基準は“完璧”より“納得感”で決める
我が家は単純な折半ではなく、家族の人数比(4対2)を考慮して、僕たちが多めに負担しています。
正直、完全な公平を数学で作るのは難しいです。共働きで日中不在の家庭と、日中も在宅が多い家庭では、光熱費の使い方が違うからです。
だからこそ「毎月の精度」よりも、後から言い争いにならないルールを優先しました。
手順3:ルールは“紙1枚”で残す(言った・言わない防止)
決めたことは、ノートでもスマホメモでもOKなので、残すのが大事です。
我が家は冷蔵庫に貼るスタイルが合っていました。見える場所にあると、確認コストが下がります。
義両親と分担している費用項目(我が家の実例)
折半(ただし4:2で多めに負担)しているもの
- 水道光熱費(電気・ガス・水道)
→ 基本は折半ベース。ただし人数比を考慮して4:2で僕たちが多めに負担しています。
※電気・ガスは使用量が増えると単価が上がることもあるので、「人数が増えた=単純に割って安くなる」とは限りません。 - 浄化槽代
→ 年1〜2回の清掃費も含めて分担。忘れた頃に来るので、将来費として扱うとラクです。 - 家電買い替え(洗濯機・冷蔵庫・掃除機などの共用物)
→ “誰が主に使うか”と“置き場所”を確認して、共用物だけ折半対象にしています。 - 日用品(洗剤・トイレットペーパー・ティッシュ等)
→ 基本は折半。ただし、ふるさと納税を使う場合は僕たち側で手配して、家計全体の節約に回しています。 - 食費(共同での食事が多い)
→ こちらも4:2の割合で分担。共働きなので、平日の義母の料理にかなり助けられています。
義両親が負担しているもの
- 固定資産税:家の所有者が義両親のため
- 火災保険料:建物保険は義両親の契約で維持
- 固定電話・インターネット代:契約・支払いは義両親側
固定電話に関しては、今はスマホが主役なので「本当に必要か?」は一度話し合ってもいいと思います(迷惑電話対策の観点でも)。
項目別|同居で変わった生活費のリアル(光熱費・食費・日用品・通信費)

光熱費(電気・ガス・水道):人数より“在宅時間”で決まりやすい
同居で分かりやすく増えやすいのが電気代です。我が家の場合、義両親は日中も在宅が多く、冷暖房やテレビなどの稼働時間が長め。
ここで大事なのは、「増えた/減った」より先に“納得できる分担基準”を作ることでした。完璧に測れないからこそ、揉めない形に寄せるのが正解だと思っています。
食費:増えやすい家庭/減りやすい家庭がある
食費は同居で必ず下がる…というより、家庭の運用次第です。
- 増えやすい:食の好みが多様/外食が増える/“ついで買い”が増える
- 減りやすい:共同購入ができる/作り置きが増える/献立が固定化できる
我が家は、近年の物価高もあって金額自体は上がりました。ただ、外食や惣菜に頼る回数が減った分、家計がブレにくくなった実感はあります。
日用品:ふるさと納税×まとめ買いが“揉めにくい節約”だった
二世帯同居は日用品の消費スピードが上がるので、買い足しの回数が増えると地味にストレスになります。
そこで我が家は、トイレットペーパーやティッシュなどの消耗品は、ふるさと納税やまとめ買いで「切らさない運用」に寄せました。
節約だけでなく、買い物の手間と会話コストが減るのが大きかったです。
楽天ふるさと納税で購入した日用品については、別記事で紹介しています。
通信費(回線・スマホ・固定電話):同居を機に“名義と支払い”を棚卸し
本文の比較表では「ネット代が0円(義両親負担)」のように見えますが、読者さんが気になるのはここだと思います。
- ネット回線は誰名義?支払いは誰?
- 固定電話は今も必要?(迷惑電話対策も含む)
- スマホ代は世帯ごと?まとめる?
ここを放置すると、「使ってないのに払ってる」「名義が分からない」みたいな小さなモヤモヤが積み上がります。
同居開始は、固定費を整理する最高のタイミングでした。
同居前後でかかった生活費の比較【実数値公開】
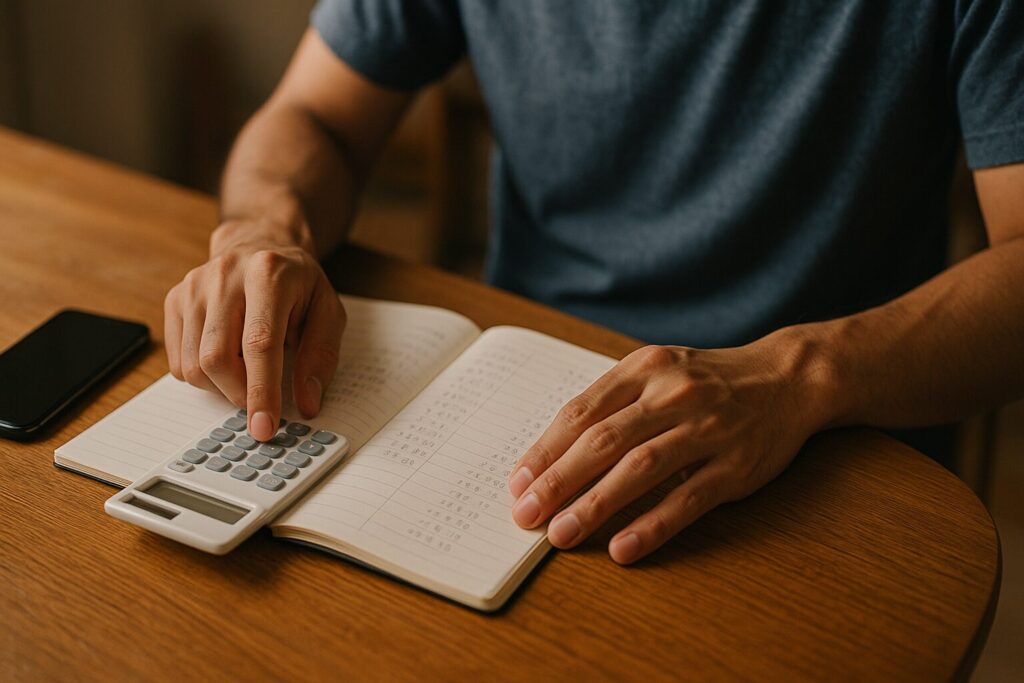
二世帯同居を始める前と後で、実際にどれくらい生活費が変わったのか。僕の家庭(夫婦+子ども2人)を例に、項目別に比較します。
| 項目 | 同居前(月額) | 同居後(月額) |
|---|---|---|
| 家賃(住宅ローン含) | 61,000円 | 0円 |
| 電気代 | 8,000円 | 11,000円(折半・4:2) |
| ガス代 | 11,000円 | 4,000円(折半・4:2) |
| 水道代 | 9,000円 | 8,000円(折半・4:2) |
| 通信費(ネット) | 5,000円 | 0円(義両親負担) |
| 食費 | 60,000円 | 75,000円(4:2で分担) |
| 日用品 | 6,000円 | 3,000円(ふるさと納税活用) |
| 合計 | 約160,000円 | 約101,000円 |
結果として、月あたり約6万円の節約になりました。年間に換算すると70万円以上。これは家計にとってかなり大きい差です。
見落とし注意|将来的な大きな出費(修繕・家電)をどうする?

日々の生活費に目が向きがちですが、将来必要になる「住まいの維持費」も頭に入れておきましょう。
- 修繕費:外壁・屋根・給湯器など
- 家具・家電の更新:冷蔵庫、洗濯機などは寿命に合わせて分担計画を
- シロアリ対策や排水管清掃などのメンテナンス費
こういった修繕費は10年、15年単位で大きな負担になります。僕が大事だと思うのは、「誰が払うか」より先に「どう決めるか」を決めておくこと。
我が家の落としどころ:共用メリットがあるものは“将来費”として話す
たとえば外壁塗装や給湯器は、家全体に関わるので“共用”になりやすいです。だからこそ、次のどれかに寄せると話が進みます。
- 案A:一定額を毎月積立して、将来費に充てる
- 案B:相場を把握して、タイミングが来たら都度協議する
- 案C:所有者(義両親)負担、ただし一部支援(家計状況に応じて)
“正解”よりも、家族が納得できる形を先に作るのが一番です。
住まい側の工夫やリフォームについては、こちらの記事も参考になります。
ストレスを減らす家計運用|見える化・窓口・精算のコツ
金銭的なストレスを減らすには、次の3つが効きました。
- 家計簿で共有分だけ見える化(月末の精算がラク)
- 日用品は“切らさない運用”(買い足し会話が減る)
- 大型出費は都度確認(信頼貯金が増える)
我が家の役割分担:窓口を分けて、摩擦を減らす
基本的に日々の家計管理は僕が担当しています。
義両親とのやり取りは、水道光熱費は僕、食費や日用品は妻が窓口になるようにしています。
- 水道光熱費の請求は月1回まとめて共有
- 共有物の購入は事前に相談(例:洗剤・米)
- 大型出費(家電など)は家族会議で決定
お金のことでトラブルになると信頼関係が崩れやすいので、細かくても“都度確認”を意識しています。
同居ストレスを減らす考え方は、こちらに詳しくまとめています。
向いてる人・向かない人|節約だけで決めない判断軸

二世帯同居は家計メリットが大きい反面、相性や住環境でしんどさも変わります。
向いてる人
- 生活費を下げつつ、子育ての助けを得たい
- ルールを決めて運用するのが苦ではない
- 多少の気遣いより、家計の安定を優先したい
向かない人
- お金の話をするのが極端に苦手(先延ばししがち)
- プライバシーが最優先で、共有空間がストレスになりやすい
- 生活リズムが大きく違い、衝突しやすい
メリット・デメリットを俯瞰して判断したい方は、こちらの記事もどうぞ。
また、プライバシーを重視するなら「完全分離型」の考え方も参考になります。
よくある質問(Q&A)
Q. 折半って結局、何を基準にすればいい?
A. 我が家は人数比(4:2)をベースにしました。完璧な公平より、家族が納得できて続くルールが大事です。迷ったら「固定費は契約者が持つ」「変動費は比率で分ける」「将来費は別枠で話す」の3分類がおすすめです。
Q. 食費が増えたら不公平にならない?
A. 増える可能性はあります。だからこそ「共同購入の範囲」「外食の扱い」「嗜好品(お菓子・お酒等)の扱い」を最初に決めると揉めにくいです。
Q. 家電の買い替えは誰が払うべき?
A. “共用物だけ分担”が分かりやすいです。置き場所・使用頻度・主に使う人を基準に線引きすると、納得感が出ます。
Q. 同居って節約以外に何がよかった?
A. 僕は「何かあっても安心」という感覚が大きかったです。子どもの面倒を見てもらえるのも助かります。ただし、プライバシー確保とルール設定は必須だと思います。
まとめ|二世帯同居は“節約”よりも、続けられるルール設計がカギ

僕が実際に二世帯同居をして感じたのは、生活費の節約以上に、家族としての支え合いが生活を豊かにしてくれるということでした。
一方で、同居を快適に続けるには「感謝」と「思いやり」だけでなく、お金のルールを先に決めておくことが本当に重要です。
これから同居を検討している方は、ぜひ家族全員で話し合いながら、「金銭面」と「心の距離」のバランスを取ってみてください。